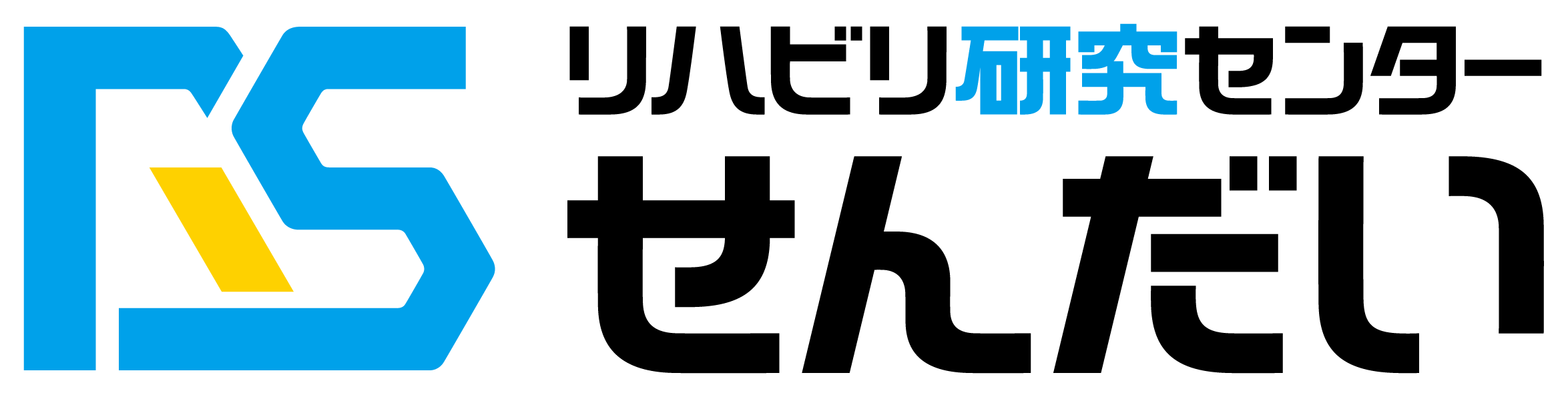退院後「手がよくならないなぁ」とお悩みの方はいらっしゃいませんか?
リハビリ研究センターせんだいでは、公的保険外の自費リハビリ施設として、手に後遺症が残った方も多くいらっしゃいます。そして、「手がもっと良くなればいいんだけど…」と皆様と同じように悩んでいます。
今回は、当施設でも利用している、自主トレとして広く販売されているリハビリ機器「まいリハ(Rehands)」を効果的に活用した、リハビリアイデアをご紹介します。
「まいリハ」って聞いたことありますか?
「まいリハ」は、エルエーピー社が制作した手指リハビリ補助ロボットです。手指の屈伸運動を空気の吸い込みと排出で自動で行うハンドリハビリ機器となっております。脳卒中後等に麻痺が存在する手に装着することで、基本的には関節可動域の拡大を目的に開発されました。


しかし、「まいリハ」にはまだまだ可能性があります!
リハビリ研究センターせんだいでは、感覚的な再教育を求めながら、運動イメージと合わせて行っており、多くの方に運動学習の促通が認められました。
感覚の「ある」「ない」でリハビリの方法も変わる
脳梗塞後遺症で「手が動かしにくい」「手が麻痺している」といった言葉を用いているものの、その状態は千差万別です。「動いている感じがする」、「動いているのはわかるけど実感が伴わない」、「動いていることが全く感じ取れない」など様々なんです。ですので、一様に同じように「まいリハ」で自主トレしてもその効果もまた様々な結果となります。一例にはなりますが、大きく2つに分けてご紹介しますね。
■ 動いている感覚が「ない」場合
目的:ご自身の手が「動いている」「触れている」といった感覚的な情報を脳へ届ける
アプローチ例
①視覚的フィードバックの活用:鏡や画面に動く「手」を映像的に映し出す。実際に動いていつことを視覚的に確認する作業を大切にする。
②運動イメージとの組み合わせ:「今から手をグーにする」といったこれから動いて得られるであろう感覚を予測します。これが運動イメージの入り口になりますので、実際に遠くに感じる感覚にしっかり耳を澄ます作業が重要となります。脳が運動の前に行っている準備運動を育てるイメージです。
③触覚情報との組み合わせ:柔らかいスポンジなどを握ってもらい、「どんな感じがするか?」という自分にしか分からない感覚に耳を傾けながら運動とリンクしてみます。
④振動や聴覚情報による気づき:運動時に聴覚情報や振動刺激を加えることで感覚的荷重を促します。
■ 動いている感覚が「ない」場合
目的:「感じる手」から「出来そうな気がする手」へ。「動かしている実感」を育てる
アプローチ例
①日常的物品の使用:ペン・洗濯ばさみなど日常的に使用する物品動作を利用した運動感覚を促す。
②リズム感覚の付加:音楽やメトロノームに合わせた手指の運動を利用する。運動のスムーズさを目指し、単純な他動的な運動から能動的な運動への準備を行う。
③閉眼:視覚遮断の環境下で手指からのダイレクトな運動感覚へ注意を向ける。
自由度の高い自費リハビリだからこそ可能となる深いアプローチ
「保険内でのリハビリでは物足りない」「もっと実用的なリハビリが欲しい」という方へ。私たちは皆様お一人お一人の状態に合わせたプログラムをご提供いたします。対面で行うリハビリだけでなく、「まいリハ」などを使用した自主トレのメニューも高い質でご提案いたします。
ぜひ、お問い合わせ下さい。